 会計法令の解説
会計法令の解説 【官公庁の契約書ルール】契約書が不要になる金額や契約確定の条件をわかりやすく解説!
契約書を省略する場合の根拠法令、民法の契約成立と契約確定の違いです。官公庁を当事者とする契約は、原則として契約書を作成します。一定金額以下の場合のみ契約書を省略できます。地方自治体は、契約書を省略できる金額が、それぞれで異なります。
 会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説  営業担当
営業担当 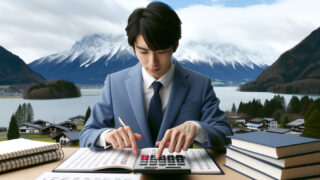 会計法令の解説
会計法令の解説  会計法令の解説
会計法令の解説