官公庁の契約業務において、最も重要なキーワードの一つが「予定価格」です。
入札公告や入札説明書を読むと、「・・予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札とする・・」などの文言が頻繁に登場します。
しかし、実際にその意味を正確に理解している人は意外と少なく、「なぜ予定価格を設定するのか」「どのように作成されるのか」「漏えいしたらどうなるのか」を曖昧にしたまま、日常の業務を進めてしまう担当者も少なくありません。
予定価格とは、発注者である官公庁が、契約を結ぶ前にあらかじめ「この契約に対して支払ってもよい金額の上限」を定めたものです。
つまり、「これ以上の金額では契約できない」という明確な基準です。
この記事では、予定価格の意味・作成方法・法的根拠・管理上の注意点を、官公庁の会計実務経験者の視点から、初心者にもわかりやすく解説します。
予定価格とは何か ― 公正な契約を支える基準価格
予定価格の基本的な定義
予定価格とは、官公庁が契約を締結する際、過去の取引実績、参考見積書や積算資料などをもとに算定した「契約の上限価格、適正価格の限度額」のことです。
入札の場合は、「この金額を超える入札は対象外」という基準となり、随意契約でも「妥当な価格で契約したか」を判断する重要な根拠になります。
たとえば、公共工事や物品購入などの契約では、契約締結前に契約担当者が市場価格や原価を調査し、参考見積書や過去の契約実績を考慮して予定価格を設定します。これにより、税金の無駄遣いを防ぎ、公正な契約を行うことができるのです。
予定価格を設定する目的
予定価格を設定する最大の目的は、適正価格の確保にあります。
官公庁の契約は、国民の税金を財源として行われます。そのため、基準もなく契約金額を恣意的に決めてしまうと、適正価格なのか不明になり、税金の無駄遣いになりかねません。
予定価格を事前に設定しておくことで、次のような効果があります。
契約価格の妥当性を確保できる
入札者間の公平な競争条件を維持できる
契約担当者の裁量を制限し、不正を防止できる
契約結果に対して説明責任を果たせる
このように、予定価格は単なる「目安」ではなく、適正価格の上限を示しており、公正な取引を守るための“防波堤”なのです。
予定価格の法的根拠と制度上の位置づけ
会計法令における根拠
予定価格の設定は、国の会計制度において明確に位置づけられています。
予算決算及び会計令第80条では、「入札を実施する場合には、予定価格を定めなければならない」と規定されています。随意契約の場合も同様です。
予算決算及び会計令
(予定価格の決定方法)
第八十条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。(予定価格の決定)
第九十九条の五 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
地方自治体は、地方自治法で予定価格の範囲内で落札とすることを定めており、随意契約も同様に予定価格を作成することを、各自治体の規則で定めています。
地方自治法
第二百三十四条
(略)3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(略)に付する場合においては、(略)契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
つまり、官公庁が競争入札を行う際は、必ず予定価格を設定しなければなりません。
落札決定には予定価格が必須
さらに、予定価格は落札決定の上限価格なので、予定価格がないと、落札決定できないのです。随意契約も同じように取り扱います。落札決定の根拠法令も確認しておきましょう。
会計法
第二十九条の六 契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
地方自治体は、上述の地方自治法 第二百三十四条 です。
このため、国・都道府県・市町村を問わず、予定価格はすべての官公庁契約における上限価格であり、基本的なルールなのです。
予定価格を定める権限者
金額が大きい契約の場合、予定価格は、支出負担行為担当官や契約担当官など、契約の執行権限を持つ職員が、予定価格調書として最終決定します。
実務上は、契約担当者(係員クラス)が市場調査や積算を行い、予定価格算出内訳書と予定価格調書を作成し、係長や課長補佐、課長など、上司の決裁を経て正式に確定されます。
この予定価格は、開札前に「予定価格調書」として文書化され、機密扱いで保管されます。予定価格調書は厚い封筒に入れ、封印し、開札直前まで金庫で保管されます。
予定価格を知ることができるのは限られた職員だけであり、外部はもちろん、他部署の職員であっても、知ることはできません。
予定価格の作成方法 ― 実務での流れとポイント
市場調査(積算資料・見積もりの収集)
予定価格を作る第一歩は、契約内容に応じた市場調査です。
物品契約であれば、複数の取引業者から参考見積書を取得したり、過去の契約実績を調べたりします。
役務契約の場合は、積算資料(労務単価、材料費、経費率など)を基に、作業員ごとに詳細な積算を行います。
官公庁が公表している積算基準や労務単価を活用することで、より正確な予定価格を算定できます。
原価計算方式と市場価格方式
予定価格の算出方式には、主に次の二つがあります。
原価計算方式:
人件費、材料費、経費、一般管理費などを積み上げて計算する方法です。主に製造契約や役務契約などで用いられます。工事契約は、国土交通省や各地方自治体が積算基準を公開しています。
市場価格方式:
市販製品など、取引実績や市場価格が明確な場合に採用される方式です。納入実績表に基づく調査、参考見積書などから設定します。
多くの契約では、これらを組み合わせて「積算根拠」を作成し、最終的に予定価格を導き出します。
予定価格算出内訳明細書の作成
予定価格を設定するときは、その根拠を明示するために「予定価格算出内訳明細書」を作成します。予定価格調書の詳細な内訳を記載します。
次のような項目を記載します。
予定価格の算定根拠(過去の契約実績、参考見積書、積算資料など)
積算明細(単価・数量・経費率など)
予定価格算出内訳明細書は、契約手続きの公正性・透明性を保つための「裏付け資料」であり、外部の検査などの際には必ず確認される重要文書です。仕様書の内容と同一であること、根拠となる数値などが明確でなければなりません。作成担当者だけでなく、誰が見ても内容を理解できるように作成します。そのため、数値の羅列だけでなく、文章で作成することも多いです。
予定価格漏えいのリスクと防止策
予定価格漏えいとは
「予定価格漏えい」とは、官公庁が作成した秘密扱いの予定価格が、入札前に外部へ伝わってしまうことを指します。
この情報が特定の業者に伝わると、その業者が予定価格ギリギリの金額で入札し、不正に落札を行うことが可能になります。
その結果、健全な競争性が失われ、税金の適正な使用が損なわれることになります。
漏えいがもたらす法的リスク
予定価格漏えいは、単なる規則違反ではなく、刑法上の犯罪に該当する場合があります。
官公庁側が業者に予定価格を教えたり示唆した場合、「官製談合防止法」や「入札妨害罪」の適用を受け、懲戒処分や刑事罰の対象となることもあります。
実際に、予定価格の情報を漏らしたことで逮捕・免職処分となった事例も多く、契約担当者にとって最も注意すべきリスクの一つです。入札の上限価格である予定価格だけでなく、下限価格である最低制限価格を漏らしても同様です。
実務上の防止策
予定価格漏えいを防ぐために、次のような基本対策を徹底する必要があります。
予定価格調書は、開札直前まで厳重に金庫で保管する
電子データの場合はアクセス制限を設け、閲覧ログを残す
業者との打ち合わせでは価格に関する発言を避ける
印刷物やメモは不要になった時点で裁断処理する
合議先などの関連部署には予定価格を共有しない
これらは、契約担当者を守るための最低限のルールです。予定価格の管理は、「正確に作ること」以上に「漏らさないこと」が重要なのです。
予定価格と落札価格の関係 ― 適正な価格を見極める
予定価格を超えた場合の対応
入札価格が予定価格を上回った場合は、落札できません。
この場合、3回ほど再度入札を繰り返し、それでも落札できなければ入札を打ち切ることになります。最安値の会社と随意契約の交渉も可能ですが、入札金額と予定価格の差が大きい場合には、入札を断念することになります。落札者がいない場合は、「不調」となります。
特に、資材価格や為替変動によって市場価格が上昇している場合は、予定価格そのものを再計算する必要があります。ただ、予定価格を修正した場合には、入札をやり直すことになり、「再度公告入札」になります。
まとめ ― 予定価格を理解することが信頼の第一歩
予定価格は、契約を締結するときの「上限価格」であり「適正価格の防衛線」です。
市場調査を十分に行い、正しく設定すれば、公平・公正な競争を生み、税金の適正使用を保証します。
一方で、予定価格が誤っていたり、漏えいしたりすれば、発注機関全体の信用を失いかねません。
契約担当者に求められるのは、「正確な積算」「適切な管理」「徹底した秘密保持」です。
また、官公庁と取引する民間企業の営業担当者にとっても、予定価格の意味を理解することで、入札戦略の立て方や見積り対応が格段に改善されます。
予定価格の理解は、単なる会計知識ではなく、「信頼される行政」「公平・公正な取引」の基礎そのものです。この記事が、あなたの職場での契約実務に少しでも役立つことを願っています。
なお、記事の内容を、さらに簡単にしたYouTube動画を音声配信しています。通勤時などにオーディオブックとして活用できます。チャンネル登録してご利用ください。
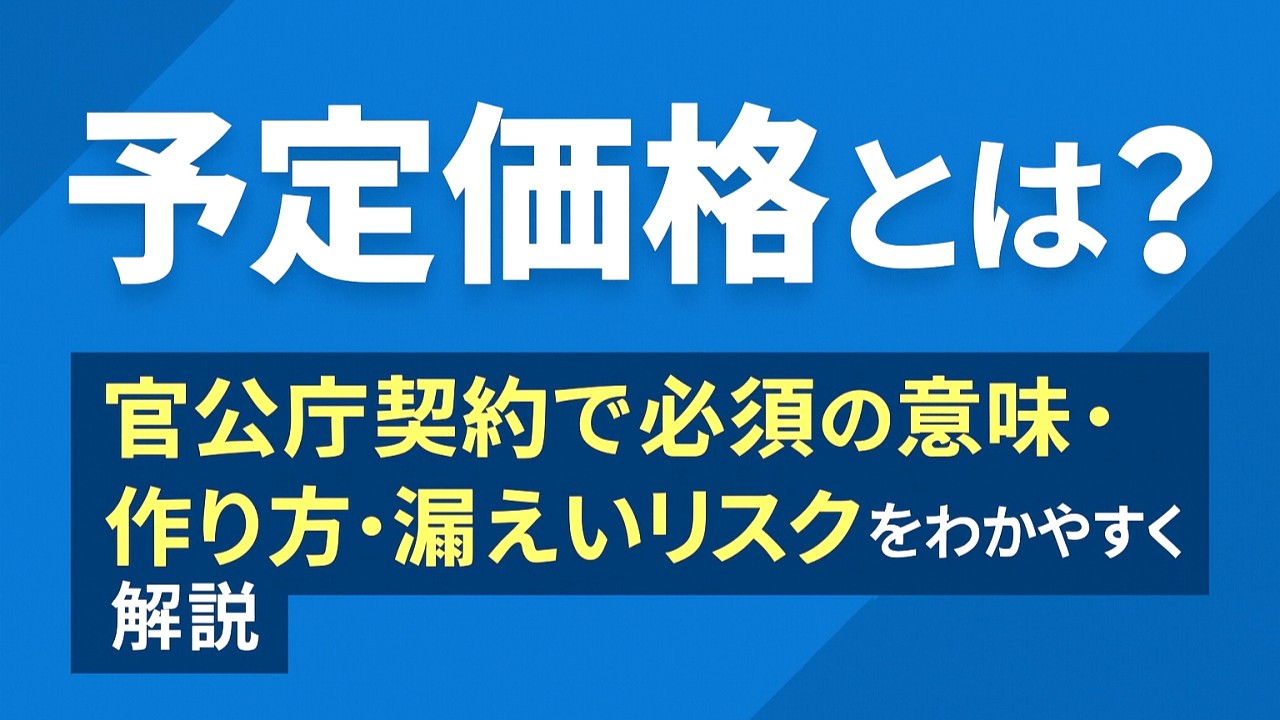

コメント