一般競争入札は、官公庁の契約方式の中でも「公平・公正性、透明性、価格競争性」を確保できる仕組みとして広く採用されています。
しかし一方で、現場の担当者や民間企業からは「一般競争入札にはどんなデメリットがあるのか」「実務上どんな点に気をつけるべきか」といった疑問の声も多くあります。
確かに一般競争入札は、不特定多数の企業が参加できる反面、価格競争が激しくなりすぎて品質が低下したり、手続きが複雑で事務負担が大きくなったり、仕様書の不備によって入札不調につながるなど、運用次第では大きなリスクを抱える方式でもあります。
また、専門性の高い契約内容では参加できる企業が限られ、競争が形骸化してしまうケースも珍しくありません。本記事では、一般競争入札のデメリットを実務経験にもとづいてわかりやすく整理し、発注者・受注者の双方が注意すべきポイントや、リスクを防ぐための対策まで詳しく解説します。
一般競争入札とは?仕組みと特徴をわかりやすく解説
「一般競争入札」とは、発注機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)が、不特定多数の事業者に対して入札公告を公開し、入札金額の中で最も有利なものを選定して契約を結ぶ方式です。これは、公的機関における契約方式の原則とされており、会計法や予算決算及び会計令、地方自治法の規定を受けて実施されています。 例えば、公共工事や業務委託、物品購入といった幅広い発注で、金額の大きい契約は、この方式が用いられています。
主な特徴は、まず「参加資格を満たせば誰でも入札できる点」です。企業規模や設立年数による制限が少ないため、比較的新しい事業者や中小企業にも参入のチャンスがあります。また、入札公告や契約内容が公開されるため、公平性・公正性、透明性が担保されるという点も特徴です。たとえば、入札経緯や落札金額の公表により、税金の使途に対して説明責任を果たしやすいというメリットもあります。
ただし、この方式を選べば無条件でスムーズというわけではありません。むしろ「多くの企業が参加できる」ことが、別の見方をすれば、さまざまな課題を伴うことにもなります。次から「一般競争入札が抱えるデメリット」を具体的に見ていきましょう。
一般競争入札に潜む5つのデメリット
価格競争が激化しすぎて品質が低下するリスク
一般競争入札では、落札者選定の基準が「入札金額の低さを重視」する「最低価格落札方式」が採用されています。このため、参加企業は「落札のためには価格を可能な限り下げる」という状況に追い込まれます。
無理な価格競争によって、利益が確保できない、あるいは履行のために経費削減や人員削減といった対応に迫られ、結果として品質や安全性が低下するというリスクがあります。実際、令和6年12月13日 閣議決定「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」13ページには次の記載があります。
「一般競争入札は、(略)その運用次第では、個別の入札における競争参加資格の確認に係る事務量が大きいこと、不良・不適格業者の排除が困難であり、施工能力に欠ける者が落札し、公共工事の質の低下をもたらすおそれがあること、建設投資の減少と相まって、受注競争を過度に激化させ、ダンピング受注を招いてきたこと等の側面もある。」
このように、価格重視の一般競争入札が、必ずしも適切な発注・契約につながるわけではなく、特に技術力・施工能力・維持管理能力が問われる案件で「安かろう悪かろう」になってしまう可能性がある点が、最大のデメリットの一つです。
入札手続きに時間と事務コストがかかる
不特定多数から広く募集をかける方式であることから、発注機関側でも「公平な仕様書作成」「入札公告」「質疑応答の実施」「同等品などの提案書類審査」「開札・落札決定」「契約締結」といった一連の手続きに相応の時間と事務負担がかかります。
発注側だけでなく、参加を検討する民間企業にも、入札参加資格の取得・更新、仕様書の確認、入札金額の積算など、かなりの時間が必要です。特に落札に至らなかった場合でも、これらの投資が回収できないというリスクもあります。「一般競争入札では準備や手続きに手間がかかる」という指摘が多いのです。
このような時間・コスト面の負担は、自治体など規模の小さい発注機関や中小企業にとっては、入札手続きを躊躇する要因にもなっています。
仕様書の不備が原因で入札不調になる
仕様書(官公庁側が求める契約内容)や、予定価格の設定が十分でないと、入札参加者ゼロ、あるいは予定価格を超えてしまう、という結果になることがあります。これらの落札者がない状態を「入札不調」といいます。簡単にいえば、入札の失敗です。
官公庁側の市場調査が不足し、仕様策定や予定価格算定の精度が低いと、適切な競争を確保できず、関係者すべてにとって機会損失・信頼損失となる可能性があります。特に、新規分野・技術要件が高度な案件・地域特性が強い案件では、仕様の不十分さが顕著に表れる傾向があります。
専門性が高い契約では、参加企業が限られる
一般競争入札では、原則として「誰でも参加しうる」点がメリットですが、逆に発注内容が高度な技術・専門的な内容・独自的な設備を伴うものである場合、参加可能な企業数が極端に限られてしまうことがあります。
例えば特許製品の修理・保守契約、特殊設備の維持管理、著作権によって保護されているプログラムの修正などでは、参加可能な企業が一社に絞られて、結果として「競争が形だけ」になってしまうことがあります。この場合、一般競争入札を実施する意義(不特定多数の参加)を十分に果たせなくなることがあります。
このような状況では、発注機関としては実質的に競争原理が働かない中で、適正な契約相手を選べないリスクを抱えることになります。
1社入札が「競争が成立していない」と誤解されやすい
一般競争入札は、不特定多数が参加可能な方式ですが、実務上は参加が1社だけにとどまる「1社入札」の発生もあります。形式的には一般競争入札であっても、競争が不十分だと批判されるケースがあり、「価格競争性が担保されていないのではないか」という外部からの疑念を招く可能性があります。
しかし、一般競争入札は、入札公告を十分な期間公開しているのであれば、競争性を確保しているといえます。参加企業側の判断として、他の契約を優先したり、採算が合わないなどの営業戦略で参加しないことも多いのです。
つまり、入札公告を見て判断しているので、価格競争が行われているわけです。一般競争入札の場合、「1社入札」は、まったく問題なく、結果論にすぎません。ただし、指名競争入札の場合の「1社入札」は問題です。指名基準が適正でないので、一般競争入札へ切り替えて、もう一度やり直す必要があります。
一般競争入札のリスクを防ぐためのポイント
一般競争入札のデメリットを理解したうえで、発注者や受注者がリスクを低減し、適正な入札・契約を実現するためのポイントを整理します。
公告期間を適切に確保する
発注機関側では、入札公告を出す際に公告掲載期間(入札参加希望者が内容を確認し準備する期間)を十分に確保することが重要です。最低でも2週間以上、できれば1ヵ月以上が望ましいです。公告期間が短いと、参加希望の事業者が仕様書・見積書を十分に準備できず、参加を断念するか、事実上の競争が制限された質の低い入札になってしまう可能性があります。
市場調査を徹底し、仕様書の精度を高める
一般競争入札の場合、最も時間のかかる作業が「仕様書の作成」です。
不特定多数の企業が参加できるよう、公平な内容で作成する必要があります。例えば、物品を購入する契約であれば、さまざまなメーカーを調べ、官公庁側の求める内容について、多数のメーカーが参加できるように仕様書を作成します。この市場調査に十分な時間をかけないと、特定の企業に偏った「不公平な仕様書」になってしまいます。
最低でも1ヵ月ほどの調査検討を行わないと、公平な仕様書は作成できません。
例えば、1週間程度で作成した仕様書は、特定の企業を対象とした内容でしか作成できず、結果的に参加企業が偏ってしまうのです。他の入札参加者からクレームが発生すれば、すぐに入札を中止せざるを得ないでしょう。
仮に1週間程度で作成した仕様書で、さらに入札公告掲載期間も1週間程度だとしたら、明らかに特定の企業と癒着していると考えられます。他の企業を排除するために、形だけ一般競争入札としている不適切な入札です。
十分に時間をかけた、多くの人が参加できる仕様書で、2週間以上の入札公告掲載期間が必須です。
予定価格の設定を慎重に行う
発注機関の官公庁側としては、予定価格を適切に設定することが、入札方式を円滑に機能させる鍵となります。予定価格をあまりにも低く設定すると、参加企業が価格を下げざるを得ず、品質低下・履行トラブルのリスクが高まります。市場動向を踏まえた適正な予定価格設定が、質の確保と競争の両立につながります。
特に注意したいのは、急激な物価高騰のときです。従来の積算方式では、対応できる民間企業がない場合などは、直前の価格動向を調べるために「参考見積書」を取り寄せて、比較検討するしかありません。あまにり従来の予定価格積算方式と開きのある見積金額であれば、2社以上の参考見積書を取り寄せて、参考見積書の金額を予定価格とせざるを得ないでしょう。
入札不調が多数見られる状況は、予定価格が社会情勢に適合していないのです。契約を進めるためには、参考見積書を基準に予定価格を設定することになります。
競争参加資格(入札参加資格)の設定を最適化
官公庁側が、入札参加資格(技術実績、保守体制など)を設ける際、過度に制限しすぎると参加企業が減少してしまい、逆に競争が成立しない原因になります。一方で、資格要件を緩くしすぎると、履行能力に劣る企業が落札してしまい、質の低下につながります。適正なバランスを取るため、過去実績・施工能力等を十分調査し、複数の企業が参加できるよう設定することが望ましいです。
民間企業が感じる一般競争入札のデメリット
発注機関である官公庁側の視点だけでなく、民間企業の立場から見た一般競争入札のデメリットについても整理します。営業担当者・受注者にとって知っておくべき視点です。
大手企業との価格競争で不利になりやすい
一般競争入札は、参加資格を満たせば誰でもチャレンジできます。そのため、大手企業との価格・技術競争になるケースが多く、中小企業や新規参入企業にはハードルが高いと言えます。価格において勝負するケースでは、資金力・設備力・人員確保力で有利な大手企業が優位に立ちやすく、小規模事業者は「無理に価格を下げざるを得ない」状況に陥りがちです。
落札しても利益率が低くなりやすい
前述の通り、価格競争が激化することで受注できても利益がほとんど残らない、あるいは赤字になるというリスクがあります。受注してから契約履行までにコストがかかる公共案件では、見積りを甘く見積もると経営を圧迫します。特に維持管理・保守対応が伴う場合、収益構造が厳しくなることもあります。
入札書類の作成負担が重い
入札参加に際して、書類提出・過去実績の提示・技術提案・電子入札の対応など、準備の手間が大変です。落札できなかった場合でも、その準備にかかった時間・人件費・事務コストは回収されないという点が、中小企業にとって心理的な負担になります。さらに、電子入札システムへの対応や仕様書の読み込み、質疑応答対応など、準備の作業量が大きくなるケースがあります。
契約成立までの期間が長く、売上管理が難しい
一般競争入札では、入札公告から書類審査、開札・落札決定・契約締結と段階を踏むため、契約成立までに1ヵ月以上かかるなど、一定の期間を要します。そのため、受注を前提にした売上計画や資金繰りを立てづらくなる場合があります。特に中小企業では、キャッシュフロー上のリスクや資金負担が発生する可能性があるため、こうしたスケジュールの読み込みも重要です。
メリットも理解したうえで最適な契約方式を選ぶことが重要
「一般競争入札」には確かにデメリットがありますが、逆に公平性・透明性・価格競争性といった大きなメリットもあります。発注機関としては、これらを理解したうえで、契約の規模・技術要件を踏まえて「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」など最適な契約方式を選ぶことが重要です。
企業側も「無理しても落札する」という視点だけではなく、入札段階から仕様書を読む・見積り精度を高める・技術要件に応えるための準備をするという視点が不可欠です。入札方式のメリット・デメリットを俯瞰的に理解することで、戦略的に活動することが可能です。今回は無理でも、次回の契約につなげるという長期的な視点が大切です。
まとめ|一般競争入札のデメリットを理解し、適正な契約を実現する
本記事では、一般競争入札が抱える主なデメリットと、それを防ぐためのポイント、また民間企業視点からのデメリットについて整理しました。重要なポイントを改めて整理します。
官公庁にとっては「価格競争による質低下」「手続き・事務コスト」「仕様・予定価格の精度不足」が大きな課題です。
民間企業にとっては「価格競争で利益が出にくい」「書類・準備の負担」「契約まで時間がかかる」などが懸念点となります。
ただし、一般競争入札には「公平性・透明性」「競争による適正価格形成」といったメリットがあり、デメリットを理解したうえで適切に運用すれば、発注・受注双方にとって有益な方式です。
官公庁の契約実務に携わる皆さま、あるいは官公庁を取引先に持つ営業担当者の皆さまにおいて、本記事が「一般競争入札のデメリットを知る」ための実務的な手がかりになれば幸いです。デメリットを理解し、適正な契約手続きを実現することで、トラブルを未然に防ぎ、発注・受注の両面で良好な結果を導くことができるでしょう。
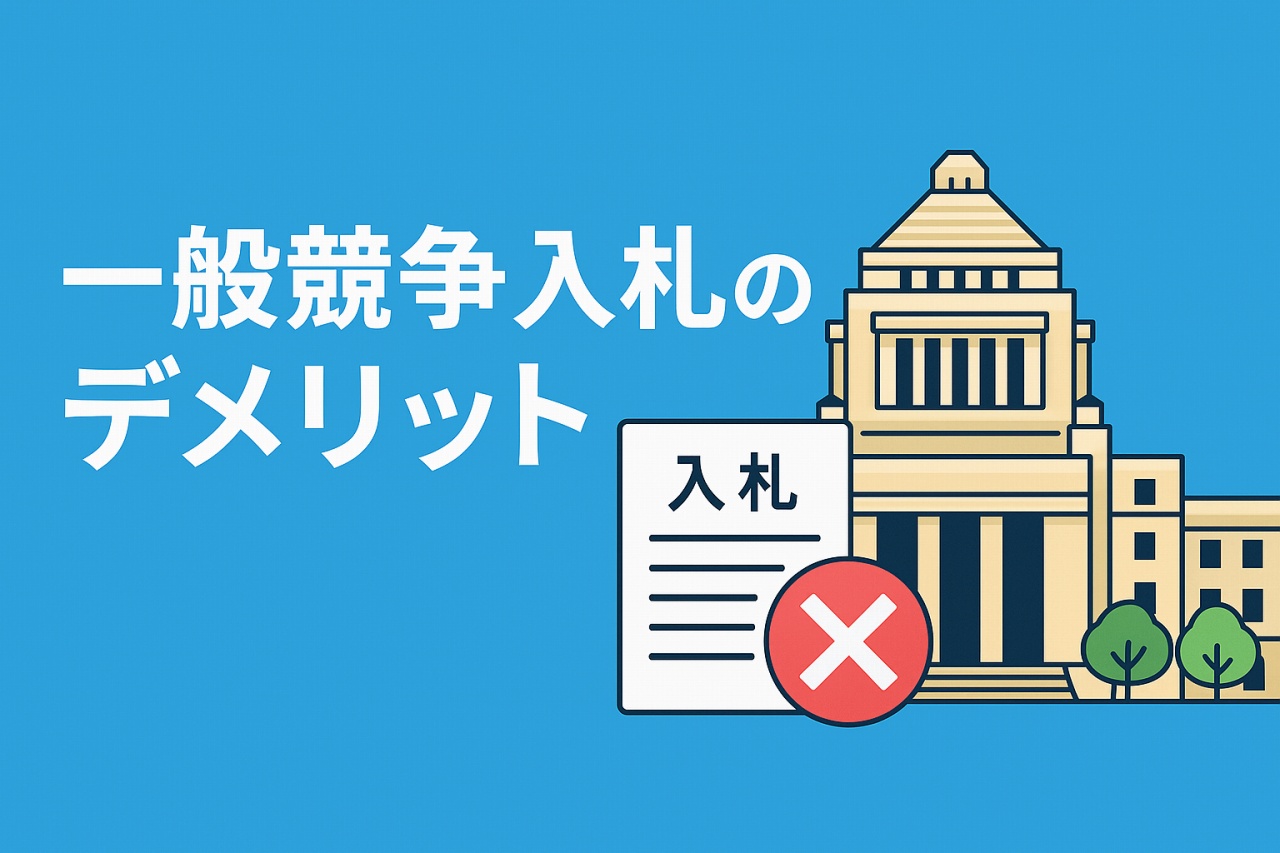


コメント