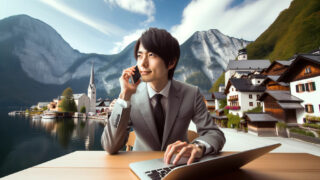 契約手続き
契約手続き 参考見積書を取り寄せる手順、参考見積書を依頼する具体的な方法
一般競争入札か、それとも随意契約できるのか、契約方式を判断するときは、契約予定金額を把握しなければなりません。また予算要求の根拠資料としても参考見積書が必要になることがあります。参考見積書を取り寄せる具体的な方法をわかりやすく解説します。参考見積書と見積書の違いを意識しておくことも大切です。
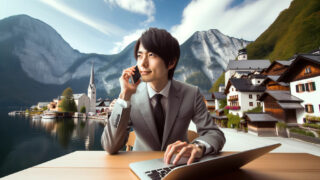 契約手続き
契約手続き  随意契約
随意契約  入札
入札  契約手続き
契約手続き  入札
入札  契約手続き
契約手続き  契約手続き
契約手続き  入札
入札  契約手続き
契約手続き  契約手続き
契約手続き