官公庁の入札手続きについての解説です。一般競争入札と指名競争入札について、それぞれの契約方式を判断する手順、書類の作成方法を具体例で解説します。仕様書の作成、入札公告、予定価格、開札、落札決定のやり方です。入札に参加したい民間企業の営業担当者にも役立つ内容です。
入札
 入札
入札  入札
入札 官公庁の入札手続きについての解説です。一般競争入札と指名競争入札について、それぞれの契約方式を判断する手順、書類の作成方法を具体例で解説します。仕様書の作成、入札公告、予定価格、開札、落札決定のやり方です。入札に参加したい民間企業の営業担当者にも役立つ内容です。
 入札
入札 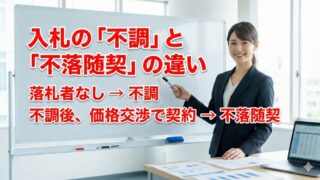 入札
入札  入札
入札  入札
入札 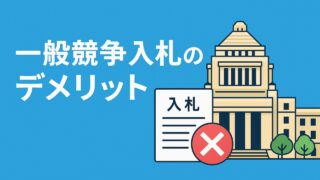 入札
入札  入札
入札  入札
入札  入札
入札  入札
入札  入札
入札