官公庁の契約方式の中でも、「随意契約」はよく耳にする言葉です。
しかし、「随意」という言葉の印象から、「自由に契約できる」「不透明な仕組み」と誤解されることも少なくありません。
実際には、随意契約は法律に基づいた正式な契約方式であり、入札と並んで行政運営を支える重要な仕組みの一つです。とくに、緊急時の対応や少額契約、専門的な技術を必要とする業務などでは、随意契約を活用することで業務の迅速化や効率化が可能になります。
つまり、随意契約には行政側にとっても、契約を結ぶ民間企業にとっても多くのメリットがあるのです。本記事では、「随意契約のメリット」を中心に、法的な位置づけや活用のポイント、注意すべきリスクまでをわかりやすく解説します。制度の正しい理解が、信頼される契約実務の第一歩です。
随意契約とは?基本の意味をわかりやすく解説
随意契約とは、国や自治体が契約を結ぶ際に、一般競争入札などの「競争手続」を経ずに、発注者の判断で特定の業者と直接契約するなど、契約締結を迅速に行う方式のことです。
一般競争入札が「原則」なのに対して、随意契約は「例外的に認められる契約方式」として位置づけられています。
国の場合は「予算決算及び会計令」、地方自治体の場合は「地方自治法施行令」に、その根拠が明記されています。これらの法令では、随意契約が認められる具体的な条件が規定されており、勝手に利用できる制度ではありません。
随意契約にはいくつかの種類があります。代表的なものを挙げると、以下のとおりです。
| 区分 | 内容 | 典型的な使用例 |
|---|---|---|
| 少額随意契約 | 契約金額が一定の基準以下であり、入札手続きを行うコストが不釣り合いな場合に認められる方式 | 備品購入、軽微な修繕、消耗品の購入など |
| 競争性がない随意契約 | 技術的独自性や特許、実績などにより特定の業者しか履行できない場合に適用される方式 | 特許製品の導入、専門機器の保守、特定メーカー指定の修理など |
| 緊急随意契約 | 災害や事故など、時間的猶予がない状況で緊急的に契約が必要な場合に行われる方式 | 台風などの自然災害の復旧工事など |
| 不落随契(ふらくずいけい) | 入札を行ったものの、落札者がなかった場合に実施される方式 | 複雑な仕様、物価の高騰などで予定価格を超えてしまう場合 |
このように、随意契約と一口にいっても、実際には複数のケースが存在し、適用できる根拠と手続きが異なります。
随意契約のメリット:国・自治体側の利点
手続きが迅速で柔軟に対応できる
随意契約の最大のメリットは、手続きが非常にスピーディーであることです。
一般競争入札を行う場合は、公平な仕様書の作成、入札公告の公開、予定価格の作成、入札、開札、落札者決定といった複数の工程を踏む必要があります。これらには通常、契約を締結するまでに、2か月以上の期間を要します。
一方、随意契約では、こうした厳密な仕様書の作成や入札公告の公開を省略し、官公庁側が選んだ「信頼できる会社」3社と、直接交渉で契約を進めることができるため、短期間で契約を成立させることができます。
「信頼できる会社」は、官公庁との契約実績が多数あり、会計法令を理解しているので、提出する書類などもミスがありません。官公庁側の意向を把握しているので、細かい説明や、時間のかかる質疑応答も必要ありません。利益至上主義ではなく、公共の利益を重視した取引が可能な会社です。
たとえば、金額の大きい契約の場合でも、3社の見積書を比較する「見積もり合わせ」によって、契約を締結するまでに2週間程度です。金額の小さい契約であれば「見積もり合わせ」も省略して2~3日で契約締結が可能です。
専門性や著作権などの独占的権利を有する企業を選べる
官公庁が実施する業務の中には、特定の技術やノウハウ、知的財産を持つ企業でなければ対応できないものがあります。
たとえば、特定メーカーの機器にしか対応できないメンテナンス業務や、著作権のある独自ソフトウェアの保守契約などです。こうしたケースでは、一般競争入札を行っても、結局そのメーカーしか対応できません。
このようなときに随意契約を活用すれば、実務的に最適な相手と契約を結ぶことができ、業務の継続性や品質を確保できます。「競争性がない随意契約」は、まさにこのような状況を想定して設けられた制度です。
少額契約による事務の効率化
少額随意契約の制度は、官公庁の契約手続きを効率化するうえで非常に重要です。
例えば、1~2万円程度の消耗品を購入するたびに入札を行うのは非現実的です。厳格な仕様書を作成し、入札公告を出し、開札するまで2か月も必要です。入札手続きの労力と時間の方が、購入費をはるかに上回ってしまうからです。入札担当者の人件費だけで数十万円を超えます。
このような場合、少額随意契約を活用すれば、必要なものを迅速に調達できます。
法令上も、予定価格が一定額以下であれば、随意契約で処理することが認められています。2025年4月の改正では、随意契約が可能な金額の上限が引き上げられ、物品購入契約は300万円以下になりました。今後はさらに活用の幅が広がると考えられます。
随意契約のデメリットと注意点
公平性・透明性の確保が課題になる
随意契約は、特定の業者を直接選定できる仕組みであるため、外部から見ると「不透明」「えこひいきではないか」と誤解されやすいという側面があります。
実際、過去には不適切な随意契約が監査で指摘された事例もあります。こうした疑念を避けるためには、随意契約理由書の作成や決裁文書での明確な説明が欠かせません。
契約担当者は、「なぜこの業者を選定したのか」「競争入札を行わなかった理由は何か」を文書で残し、監査や会計検査院の調査に耐えられるよう整備することが求められます。
価格の妥当性を確認する必要がある
随意契約では、一般競争入札のように、不特定多数の者による価格競争が行われないため、価格が高くなるリスクが否定できません。
このため、たとえ随意契約であっても、可能な範囲で3社の見積書を取り寄せ、価格妥当性を確認する「見積もり合わせ」が必要です。
また、予定価格の作成にあたっては、物価資料や過去の契約実績を参考にするなど、根拠を明確にしておくことが重要です。
長期的に同一業者へ偏るリスク
随意契約を長年同一の業者に繰り返すと、「特定の業者が優遇されている」との疑念が生じる場合があります。
同一業者への依存は、契約内容の見直しやコスト削減の機会を失うことにもつながります。
このため、契約可能な会社が多数ある場合は、「見積もり合わせ」を依頼する会社を変えることが重要です。
随意契約を正しく運用するための実務ポイント
根拠法令に基づく判断を行う
随意契約は「例外的に認められる契約方式」であるため、まず根拠法令に照らして適用可能かを確認することが重要です。
契約金額の基準、競争性の有無、緊急性など、いずれも明確に判断する必要があります。
契約担当者は、案件ごとに該当条項を確認し、随意契約を選択する理由を決裁文書に明記します。特に「見積もり合わせ」ができない、「競争性がない随意契約」の場合には、随意契約理由書を作成しなければなりません。
随意契約理由書の作成
随意契約を実施する際には、「随意契約理由書」または「業者選定理由書」を必ず作成します。
この書類には、次のような事項を記載します。
官公庁側が必要とする契約の目的、内容・条件
契約内容に対応できる会社の調査、比較表
選定した業者名および選定理由
これらを明記しておくことで、監査や検査の際に合理的な説明が可能になります。
3社の見積書取得と価格確認
少額随意契約であっても、金額の大きい契約の場合、実務上は「見積もり合わせ」を行います。
3社の会社から見積書を取り寄せ、最も有利な価格を提示した業者を選定することで、透明性と公平性を確保できます。
見積書を依頼するときには、仕様書を添付し、比較しやすい形で提出してもらいます。比較した見積書は、合格・不合格の表示をして、保管することが重要です。
契約情報の公開と説明責任の確保
多くの官公庁では、随意契約の情報をホームページで公表する仕組みを導入しています。
契約金額、契約相手、契約理由などを公開することで、透明性を高め、住民からの信頼を得ることができます。
契約担当者は、公開用データの作成や情報整理にも注意を払いましょう。
まとめ:随意契約は「不透明」ではなく「効率性重視」
随意契約は、一般競争入札に比べて、契約を締結するまでの期間を大幅に省略できる、効率性重視の制度です。
契約の相手方を選定するまでの期間が、一般競争入札では2か月以上、随意契約は2~3日です。圧倒的な効率性が随意契約のメリットです。
しかし、随意契約が認められるのは、法律に基づいた場合だけであり、恣意的に使えるものではありません。
また「競争性がない随意契約」の場合には、裏付け資料と共に、その理由を明確に説明することが求められます。
随意契約の真のメリットは、迅速に契約を締結できるといった、行政運営を支える実務的な効果にあります。
一方で、透明性・公平性を欠けば、制度の信頼性が損なわれます。
だからこそ、契約担当者には「適法かつ説明可能な運用」を徹底する姿勢が求められるのです。
民間企業の営業担当者にとっても、随意契約は大きなビジネスチャンスです。
ただし、単に「入札なしで契約できる」仕組みではなく、「行政が選びやすい実績・信頼・技術力」を備えてこそ、随意契約の対象となります。
公的組織と取引するうえで、法令を理解し、公共性を意識した行動を取ることが、長期的な信頼関係の構築につながります。
随意契約は、不正の温床ではなく、行政にとっての「正当な効率化の仕組み」です。
そのメリットを正しく理解し、適正な手続きをもって運用すれば、官民双方にとって大きな価値をもたらす契約方式なのです。
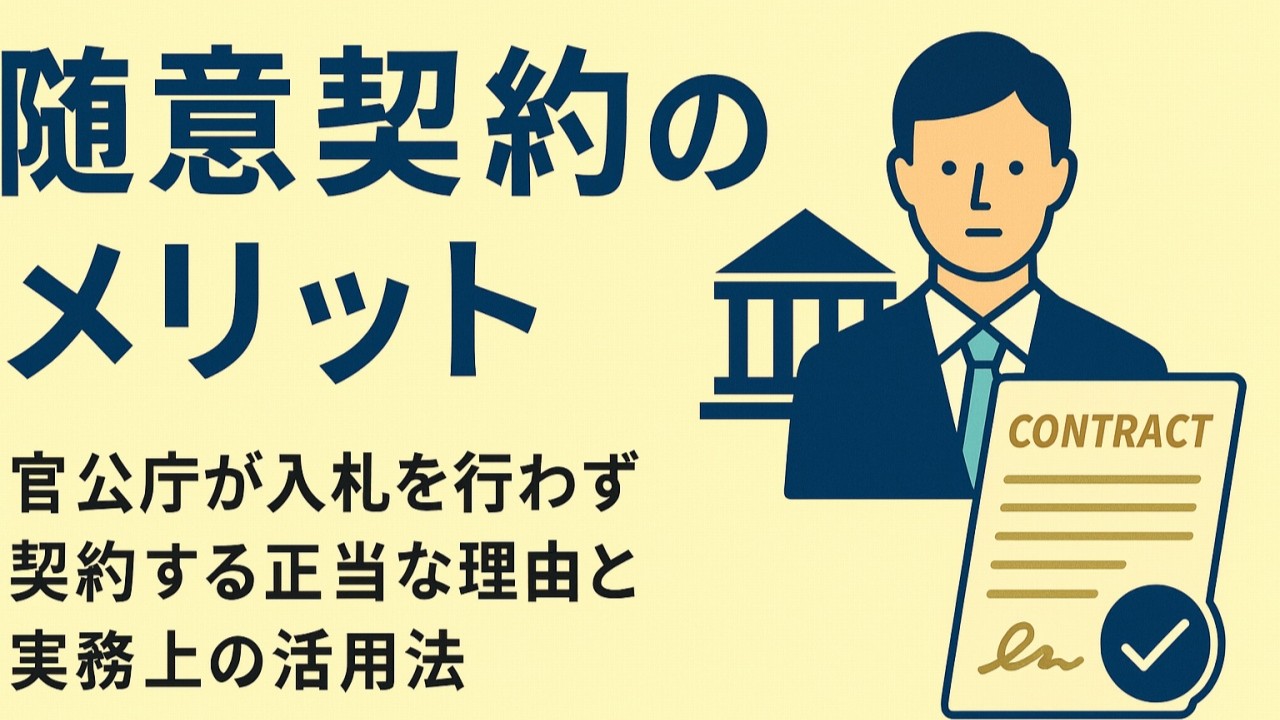


コメント